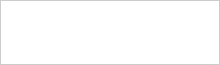通巻145号 第37巻 第1号
|
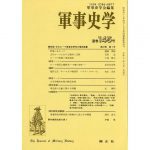 |
| (巻頭言)「なりそこないの野砲手の弁」 | 吉村 忠典 |
| 特集にあたって | 樋脇 博敏 |
| 古代ローマにおける戦争と宗教 | 毛利 晶 |
| ローマの軍隊と軍医制度 | 小林 雅夫 |
| (研究ノート)ローマ帝国主義研究 --回顧と展望-- | 長谷川 岳男 |
| (書評)塩野七生『ローマ人の物語VI パクス・ロマーナ』 | 米山 宏史 |
| 野村實前会長を思う | 伊藤 隆 |
| (研究ノート)太平洋戦争末期の戦災処理 | 古川 由美子 |
| (研究余滴)軍法務の文献に関する問題 | 北 博昭 |
通巻146・147合併号
|
 |
| (巻頭言) | |
| 満州事変七〇周年に寄せて | 高橋 久志 |
| 近代軍事遺産・遺跡の保存 | 安岡 昭夫 |
| (第一篇 思想的潮流) | |
| 「満州事変」の性格 | 臼井 勝美 |
| 満州事変と「八絋一宇」 --石原莞爾を中心に-- | 三輪 公忠 |
| 満州領有の思想的源流 | 秦 郁彦 |
| 石原莞爾の満州事変 --満州事変のモデルはむしろロシア革命であった-- | 野村 乙二朗 |
| 石原構想の限界と可能性 | 荒川 憲一 |
| (第二篇 政治・外交からの視座) | |
| 満洲事変直前の日中間の懸案交渉 | 浜口 裕子 |
| 「宥和」の変容 --満州事変時の外務省-- | 小池 聖一 |
| 一九三二年未発の「満洲PKF」? --リットン報告書にみられる特別憲兵隊構想- | 等松 春夫 |
| 近代日本の政治過程と「九・一八」事変 | LI Shuquan(伊藤信之訳) |
| 九一八事変と中国の政局 | ONG Weimu(伊藤信之訳) |
| 九一八事変とワシントン体制の動揺 --日本の東アジアにおける政戦略の変化を中心として-- | 熊 沛彪(劉紅訳) |
| (第三篇 陸海軍の動向) | |
| 満州事変における関東軍の固有任務とその解釈・運用問題 | 白石 博司 |
| 海軍の強硬化と満州事変 --昭和八年前後の日本海軍-- | 影山 好一郎 |
| <研究ノート> | |
| 満洲事変期陸軍の対ソ認識の一面 --真崎甚三郎を中心に-- | 白石 仁章 |
| <研究余滴> | |
| 熱河・関内作戦雑感 | 米本 敬一 |
| <史料紹介> | |
| 重光駐華公使報告書 | 服部 龍二 |
| 安藤利吉兵務課長「滿洲事變ノ發端ニ就テ」 | 白石 博司 |
| 参謀本部編『満州紀行』 | 安達 将孝 |
| <書評> | |
| L・ヤング(加藤陽子他訳)『総動員帝国―満洲と戦時帝国主義の文化― 』 | 高橋 久志 |
| 細谷千博、イアン・ニッシュ監修、平間洋一、イアン・ガウ、波多野澄雄編『日英交流史 1600―2000 3 軍事』 | 中山 隆志 |
| 軍事史関係史料館探訪(29)石原莞爾元陸軍中将関連史料館 | 横山 久幸 |
| (文献目録) 片倉 衷 文書目録 | |
通巻148号 第37巻 第4号
|
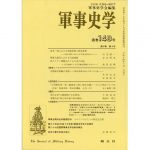 |
| (巻頭言)アカデミック・フリーダムということ | 杉之尾 宜生 |
| 忠孝一致における軍隊思想と教育思想--明治末期における中学漢文教材から-- | 石毛 慎一 |
| 関東大震災における行政戒厳 | 安江 聖也 |
| 西イリアン問題をめぐる日本の対応--KLM機による兵員輸送問題を中心に-- | 池田 直隆 |
| (研究ノート)北朝鮮兵器廠の発展--平壌兵器兵器製造所から第六五工場へ-- | 木村 光彦、安部 桂司 |
| (書評)黒沢文貴『大戦間期の日本陸軍』 | 小林 道彦 |
| (書評)東郷尚武『海江田信義の幕末維新』 | 亀掛川 博正 |
| 安井久善元会長を悼む | 近藤 新治 |
| (史料紹介)「日清戦史第一第二編進達ニ関シ部長会議ニ一言ス」(明治三六年一月起 参謀本部 部長会議録 七月一日) | 五十嵐 憲一郎 |
| 軍事史関係史料館探訪(30)ベルリンのふたつの歴史記念館 | 原 信芳 |
在庫のある号につきましては、出版元の錦正社で購入できます。以下のホームページで在庫をご確認の上、錦正社に直接お申し込み下さい。
<https://kinseisha.jp/mhsj>