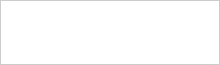通巻129号 第33巻 第1号
|
 |
<特集・古代ギリシア軍事史研究の現段階> |
|
| (巻頭言)「軍事史学と平和の理想」 | |
| 特集にあたって | 森谷 公俊 |
| アテナイ帝国主義と植民–イオニア人の母市アテナイ– | 前野 弘志 |
| ペリアンドロスの法とアテナイ最富裕市民–前四世紀中葉のアテナイ海軍に関する一考察 | 伊東 七美男 |
| ペルセポリス王宮炎上事件とアレクサンドロス | 森谷 公俊 |
| (研究動向)古代ギリシア軍事史研究の新動向 | 長谷川 岳男 |
| (書評)塩野七生著『ローマ人の物語II ハンニバル戦記』 | 石川 勝二 |
| 軍事史関係史料館探訪(15)[宮内庁書陵部] | |
| <私家版情報コーナー(29)> | |
通巻130・131号合併号
|
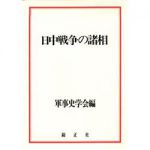 |
<130号記念特集号>
|
|
| (巻頭言)日中戦争研究の課題 | 伊藤 隆 |
| (巻頭言)20世紀の歴史の中の日中戦争 | 入江 昭 |
| (巻頭言)「統帥権独立」の起源 | 秦 郁彦 |
| 日中戦争の起源–一九三三年– | 臼井 勝美 |
| 再考「梅津・何応欽協定」 | 松崎 昭一 |
| 日中関係と日本海軍–昭和十年の中山事件を事例として– | 樋口 秀実 |
| 昭和十一年前後の日本海軍の対中強硬姿勢–「中南支方面」の事件対応を中心として– | 景山 好一郎 |
| 「中国通」外交官と外務省の中国政策–一九三五~一九三七年– | 劉 傑 |
| 廬溝橋事件勃発後の現地交渉と南京国民政府の対策 | 蔡 徳金(劉 傑・訳) |
| 日中戦争の全面化と米内光政 | 相澤 淳 |
| トラウトマン工作再考 | 宮田 昌明 |
| 日本軍による塩遮断作戦と中国「井塩基地」の抗戦運動–自貢製塩場を中心に– | 徐 勇(和田 英穂訳) |
| 南京事件–「虐殺」の責任論– | 板倉 由明 |
| 日中戦争における戦闘の歴史社会学的考察–第三七師団の事例に見る戦闘意欲の問題– | 河野 仁 |
| 戦時日本の対華電気通信支配 | 楊 大慶(波多野 澄雄訳) |
| 物資動員計画から見た日中戦争 | 荒川 憲一 |
| 中国占領地の経済施策の全貌 | 岩武 照彦 |
| 日中戦争後期における日本と汪精衛政府の「謀和」工作 | 石 源華(伊藤 信之訳) |
| 在華ドイツ軍事顧問団と日中戦争 | G・クレープス |
| アメリカの対応–戦争に至らざる手段の行使– | 鈴木 晟 |
| 日中戦争と日英関係–一九三七から一九四一年– | A・ベスト(相澤 淳訳) |
| (研究余滴)時非にして道義を叫ぶ–「対支処理根本方針」– | 森松 俊夫 |
| (研究余滴)一海軍士官による日中戦争の体験 | 末國 正雄 |
| (史料紹介)支那派遣軍總司令部編「支那事變軍票史」 | 中尾 裕次 |
| (軍事史関係史料館探訪(16)台湾における日中戦争関係資料の保存・公開状況 | 川島 真 |
| (書評)秦郁彦著『廬溝橋事件の研究』 | 波多野 澄雄 |
| (書評)波多野澄雄著『太平洋戦争とアジア外交』 | 赤木 完爾 |
| (日中戦争関係文献目録) | |
| (あとがき) | 戸部 良一・景山 好一郎 |
通巻132号 第33巻 第4号
|
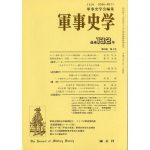 |
| (巻頭言)「言葉の時代変化と歴史家」 | 熊谷 光久 |
| レバノン戦争に見るイスラエルの戦争指導–民主主義国家の混迷– | 喜田 邦彦 |
| 珊瑚海海戦の一考察–「攻撃ヲ止メ北上セヨ」発令の経緯– | 横田 英暁 |
| (研究ノート)「大正デモクラシー」期における兵士の意識–一兵士の手記『兵営夜話』から– | 一ノ瀬 俊也 |
| (史料紹介)韓國ニ於ケル作戦計量(甲號外)–日露戦争における先遣第十二師団の作戦の準拠– | 黒野 耐 |
| (書評)広田照幸著『陸軍将校の教育社会史』 | 秦 郁彦 |
| (書評)太田弘毅著『蒙古襲来–その軍事史的研究–』 | 佐藤 鉄太郎 |
| (書評)毛利敏彦著『台湾出兵–大日本帝国の開幕劇–』 | 亀掛川 博正 |
| 軍事史関係史料館探訪(17)[ドイツの軍事博物館] | |
| <私家版情報コーナー(30)> |
在庫のある号につきましては、出版元の錦正社で購入できます。以下のホームページで在庫をご確認の上、錦正社に直接お申し込み下さい。
<https://kinseisha.jp/mhsj>