日時 平成十九年六月二日(土)~三日(日)
場所 陸上自衛隊広報センター並びに朝霞駐屯地
Ⅰ 大会概要
今年度の年次大会は、特集号(第四二巻第三・四合併号)に続き、「PKOの史的検証」を共通テーマとして、陸上自衛隊朝霞駐屯地の多大な協力を得て、二日間にわたって開催されました。今大会は、学会として現代の関心事を軍事史的視点から取り上げることを試みた初めての大会であります。第一日目は一三〇名以上の会員の参加及び非会員の聴講を得て、陸上自衛隊広報センターにおいて、特集号の執筆者によるパネル・ディスカッションを行い、続いて元防衛庁長官で衆議院議員の石破茂氏から特別講演を頂きました。第二日目は場所を駐屯地内に移し、約一〇〇名以上の会員が参加し、会員による個人研究発表が行われ、引き続き駐屯地内にある振武台記念館及び輸送学校資料館の研修を行いました。
まず、第一日目は、午前十時三十分から総会が開かれ、始めに会長挨拶が行われました。挨拶では、十八年度学会活動の総括が行われたほか、国際軍事史学会国際大会の日本開催に対する意欲が表明されました。続いて議事に入り左記の議案について審議が行われ、いずれも異議なく承認されました。
一 平成十八年度事業報告、収支決算及び財産目録報告
二 会計監査報告
三 平成十九年度事業計画及び収支予算案
続いて「平成十九年度役員人事」に入り、任期満了の永江太郎事務局長に替わり、源田孝会員が事務局長に就任することなどが決定しました。
この後、二年に一度選考される阿南・高橋学術研究奨励賞の授与が行われ、優秀論文として竹本知行会員の「大村益次郎の建軍思想―「一新之名義」と仏式兵制との関連を中心に―」が受賞しました。本論文は、大村の国家観と軍政改革を考察した点が評価されました。
午後に入り、十三時から「PKOの史的検証」をテーマに、現地で活躍された自衛官やカメラマンの参加を得て、等松春夫会員の司会で、五名のパネリストによるパネル・ディスカッションが行われました(議論の細部は、下記II参照のこと)。続いて、十六時から石破氏による特別講演が行われました。「自衛隊における国際活動の今後の展開について」と題した講演は、防衛庁長官として防衛政策を主導された石破氏でなければできないお話であり、今日の日本が抱えている国際協力や集団的自衛権の問題に対して、日本の素晴らしい特性を活かすべきであるという見識を示されました。翌日の個人研究発表に対する貴重な示唆を頂き、かつ議論を盛り上げるものとなりました。
第二日目は、まず駐屯地内の研修棟において、個人研究発表が十時十分から十二時二十分まで四会場に分かれて行われました。今回は、合計一一名の会員による報告が行われ、部会①では共通論題が取り上げられ、部会②~④では自由論題として発表者個々のテーマが報告されました。各会場ともレベルの高い報告であり、終始活発な議論が交わされました。報告者とテーマは下記のとおりであります。
部会①「共通論題:PKOの史的検証」
司会:等松 春夫
入江寿大「戦後日本のPKO政策をめぐる内政と外交―池田・佐藤政権期を中心に―」
村上友章「カンボジアPKOと日本」
コメント・討論者 増田 弘
部会②「自由論題:日米開戦過程の再検証」
司会:黒沢 文貴
佐藤元英「日本外務省の対米開戦指導―条約局および南洋局が企図した宣戦布告のシナリオ―」
塩崎弘明「『日米開戦』外交研究と関係公文書蒐集編纂の限界―その政治的または党派的背景―」
井口武夫「対米最終覚書手交遅延問題の真相と虚構―証言と遺稿の再検証の必要性―」
部会③「自由論題:欧州軍事史の諸相」
司会:根無 喜一
森口京子「ナポレオン期イタリア共和国における徴兵制」
原 信芳「ワイマール・ドイツにおける政軍関係―グレーナー文書を手掛かりに―」
守屋 純「『ジューコフ回想録』(露語版)のたどった運命」
部会④「自由論題」 司会:淺川 道夫
山本 慧「江戸湾海防における浦賀奉行の海軍構想」
長谷川怜「日露戦争の諜報活動」
広中一成「通州事件『その後』―通州治安維持会による通州復興活動―」
午後に入り、昼食を挟んで十二時二十分から四班に分かれ、振武台記念館及び輸送学校教育資料館を研修し、それぞれの会場で懇切丁寧な説明を受けました。輸送学校では、PKOを輸送という視点を切口に史的観点から取り上げており、また振武台は、旧陸軍の士官養成に関する展示で、人材育成の重要性を訴えており、まさに、現代の関心事を軍事史的視点から取り上げることを試みた今大会に相応しい史跡研修でありました(関連掲載下記III参照)。
なお、懇親会は大会初日、ホテル ガデンツァ光ヶ丘に会場を移し、十八時から行われました。懇親会には、講師の石破氏、招待パネリストの小嶋信義氏、渡邊隆氏及び朝霞駐屯地司令の千葉徳次郎氏をお招きし、総勢八〇名以上の参加を得て、打ち解けた雰囲気の中で、会員相互の親睦を深めることができました。
(文責・横山久幸)



を受賞した竹本知行会員

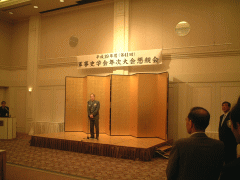
Ⅱ パネル・ディスカッションの記録
平成十九年六月二日(土)十三時から十五時四十分の間、陸上自衛隊広報センターのホールにおいて、下記の五氏により、PKO関連のパネル・ディスカッションが行なわれた。司会は会員、等松春夫である。
パネリスト:*渡邊隆氏、*小嶋信義氏、青井千由紀氏、幡新大実氏、*宮嶋茂樹氏
司会:等松春夫氏
*は招待パネリスト
最初に、報道カメラマン・宮嶋茂樹氏があらゆるPKO体験を記録したDVDの放映が行なわれた。同氏が参加した幅広い分野の記録写真であり、ユーモアを交えつつ、未整備な取材環境下で、モザンビーク現地での暑さ等のつらい体験や、住民との交流、自衛隊関係者の温かい協力支援に対する感謝を込めての説明があった。
一 パネラーによるPKO関連の所見等
(一) 渡邊隆氏(現陸幕教育部長:当時のUNTAC派遣自衛隊指揮官)
現場指揮官としてカンボジアに派遣されたが、この行動は、部隊の隊員の生死にかかわる問題、国家の存亡のかかった仕事であり、現場では徹底したリアリストとして勤務しなければならないと考えた。行動の結果に責任を取るということである。この派遣は最初の自衛隊の海外派遣であり、以後の平和に役立つと信じて行動していた。これは注目してよいと思う。一九九二年六月に国際平和協力法が整備された。八月一日に施行され、九月二十五日に現地に赴いた。約六〇〇名の隊員と車両、物資を海自、空自に輸送を頼んだ。この時感じたことが二つあった。一つは、海外で活動する初めての部隊であり、ノウハウがなく行動の枠のみが設定されていたことである。ノウハウは私自身にも国にもないのであった。ただ、個人を守るものは小銃と拳銃のみであった。現地のNGOや他国のPKO隊員をどう考えればいいのか。
二つ目は、初めての海外勤務であり、自己完結性を持った部隊の仕事ではあるが、出発から勤務に至るすべてに、つまり、現地の勤務・生活自体にも具体的なノウハウがないということであった。出発に先立つ予防注射にしても、二週間の間に、一二種類もの接種が必要であり、隊員にも不安があったのである。
PKOという言葉の響が持つ意味合いは何か。戦争でない軍隊が活動することはどういうことを意味するのか。しかもPKO自体が変化しているのである。PKOでは、もともと軍事的要素の活動形態であるものが、民生的なシビルのカラーを帯びている。わが国がどのように国際平和に、いかに係わるべきか、あるいは係わってはならないのか。何を民間に、何を自衛隊にさせるべきかという区別が必要であって、この議論をすべき大切な時期に来ているのではないか。防衛省になってPKOは本来業務になった。それまでは片手間の仕事であったため、公式的には、PKOの装備品もなく、教育もなかったといえる。しかし、今や、予想されるものは準備されるべき時代なのである。このような議論を今後、関係者間に活発にしてほしい。
(二) 小嶋信義氏(空幕情報課長:当時の在イスラエル防衛駐在官)
私は二回の中東勤務がある。①在イスラエル駐在武官(平成八年~)時代に、ゴラン高原PKOの側面支援を担当し、②在クウェート駐在武官(平成十五年~)時代にはイラク派遣に先立つ航空自衛隊先遣隊に参加した。
最初のゴラン高原の体験については、国連総派遣人員は約千名であり、そのうち自衛隊は四五名であった。自衛隊の部隊については、強い責任感、規範意識
を持っており、また、熟達した訓練などから各国から賞賛を受けた。
(三) 青井千由紀氏(青山学院大学准教授)
クウェート派遣に関しては、約二〇〇名の航空自衛官が活動した。平成十六年から現在も行なっている。C―一三〇輸送機三機を現地に派遣し、炎天下・砂嵐・異文化の中での困難な活動を行なっている。サマーワにも出張し、イラク人の中に浸透した陸自の活動を確認することが出来た。たとえば、宿営地の外側面に住民有志が自衛隊を守るために防御用ゲートを建設したことなどである。
私の体験を通じて得たことは、自衛隊のイラク派遣の意義が極めて大きいということである。ことに、対クウェート関係については、クウェートは、イラクによる被占領経験から、日本などとの二国間関係を重視しており、自衛隊の駐屯を大いに評価し、掃海艇派遣に感謝している。また、対米関係については、今回の自衛隊イラク派遣を通じて、更なる同盟関係の強化が図れたものと考えている。
今後の課題であるが、自衛隊の活動が国益に有用である点を、広報活動を強化しつつ、国民に発信していくことが必要であると考える。
国際的な戦略環境の変遷が各国のPKO・戦争以外の活動の分野での軍事ドクトリンにいかなる影響を与えるかという視点で考えたい。まず、私がPKOに学問的な興味を持った背景には、冷戦後のPKOは国際政治のうねりの中で変化しているという現実があり、紛争そのものも質的に変化していることである。また、冷戦後、PKOの次世代ドクトリンである平和支援活動という手法が確立された。このような一連の変化を踏まえ、日本としてPKOに如何に係わるべきか、再考すべき時期に来ているといえるだろう。また、PKOへの関与のための制度について検討すべき時機に来ていると思う。
欧米の場合は、軍事組織や政軍関係に関して大学等の研究機関において高次の研究がなされている。これに対し、日本の場合は、官・民および文・武における意識や知識のギャップが依然として大きいように観察している。
PKOや平和支援活動に関していえることは、これらは通常、戦争以外の目的での軍隊の使用と考えられ、特殊な訓練や準備が必要であり、通常は国際的な活動であるため、伝統的な狭義の「国防」としての「国益」概念とは異なる国益概念を基盤としている。この現実を踏まえた上で、新たな「国益」概念とは何か、またどのように日本としてこの類の活動に携わっていくのか、原則や方法(ドクトリン)についても論究が必要であろう。
各国が国連に軍を提供するにあたり、それぞれの国が、戦略環境の変化に対応した活動の形を検討すべきであって、日本の場合は、過去、主に静的環境―つまり、戦略的安定性を前提とする伝統的平和維持活動が想定される状況下(選挙監視等)での活動を主としてきたが、今後は限定的な参加となろうが、戦略的流動性の中での紛争から平和への移行という動的環境下(政府樹立等)での対応が求められてくるのではないか。
いわゆる、戦略環境の変化を正しく捉えた上でのソフト面の再構築、そして制度の見直しが必要なのである。例えば、官・民はもちろん、各省間の協力体制をいかに構築するかといった主要な課題が生じる。
また、派遣要員による犯罪等の問題にどのように対応するか、なども研究しなければならない。これらに対する対応如何で、活動そのものにネガティブな評価が生まれる危険性があるのである。
(四) 幡新大実氏(英国インナーテンプル法曹組合法廷弁護士)
国連PKOに参加する軍人が派遣先で何らかの罪(派遣国の法、受入国現地の法、または国際法の定める罪)を犯した場合、その個人の刑事責任の問い方について議論する。通常は国連と受入国の間の国連軍の地位協定と国連と派遣国の間の派遣協定により、派遣国がその刑事管轄権を行使する。実例では罪を侵した軍人を本国に送還した上、通常裁判または軍法会議で裁いている。ただし二〇〇二年に発効した国際刑事裁判所規程という条約によれば、とくにジュネーブ条約(かつて「戦時国際法」と呼ばれた規範)の重大違反やその他の国際法上の罪については、国の次元では真正または適正な裁判がなされない場合に、国際刑事裁判所(ICC)も補完的にその管轄権を行使できる。
しかし国連PKOのような国際的活動においては、現地と国際社会における国連とPKO参加部隊の信用を高めるために現地で透明性の高い裁判を行なうことが望ましい。軍法会議であれば派遣先での開廷は容易であるが透明性に問題があり、通常裁判の場合、文官の裁判官、検察官、弁護士、書記官を現地に派遣するために特別の法律が必要なだけでなく、多種多様の予防接種、危険手当その他実際的な困難が多く、どちらも一長一短ある。
かりに日本の自衛隊員が派遣先で罪を犯せば、日本の刑法や自衛隊法等に基づき日本の地方裁判所が裁くことになるが、幸いまだ実例がない。この点は、コンゴ民主共和国や西アフリカなどアフリカ部隊による犯罪の連発している場所に限らず、ソマリアや旧ユーゴスラビアなど先進国部隊までが刑事事件を起こしてしまったような活動に日本が参加せず、自衛隊の派遣先の選別を厳格に行なってきたことも評価すべきだ。
(五) 宮嶋茂樹氏(報道カメラマン)
先述のとおり、DVDによる説明。(記述省略)


Ⅲ 旧振武台を62年ぶりに訪れて―陸上自衛隊朝霞駐屯地はかつて陸軍予科士官学校のキャンパスだった
松村正義
平成十九年度の軍事史学会年次大会が陸上自衛隊朝霞駐屯地で開催されることを知った時、これにはどうしても出席しなければならないとすぐに思ったものである。なぜなら、同駐屯地は、筆者が陸軍予科士官学校の六十期生として、すでに太平洋戦争の戦局も悪化していた昭和十九年二月から一年半近くを過ごしたことのある、かつての同士官学校のキャンパス、旧振武台であったからである。同大会二日目の六月三日(日)に東武東上線の和光市駅で下車して、指示されたとおり午前九時半までに同駐屯地の北側に位置する朝霞門のすぐ傍らの広報センター前に他の参加者らと共に集合した。顧みると、同敷地内に入ったのは六二年ぶりであった。その六十余年の間に、旧振武台は現在の陸上自衛隊朝霞駐屯地としてどのように変わったのか、筆者の気持ちも少し高ぶっていた。
受付で、手続きを済ませながら、かつてこの旧振武台で一年半ほど過ごしたことが懐かしいと雑談すると、制服を着た一等陸佐で軍事史教官からその構内を案内しましょうと言われ、思い切ってお言葉に甘えることにした。午前の研究発表が終わり、午後から別途に予定されたグループでの構内案内もあったが、筆者は、同教官の運転するジープに搭乗して、広報センター前から南へ同駐屯地内を巡り始めた。まずは、かつての正門だった大泉門の方へ向かう。ただし、その大泉門は現在は使用されておらず閉められているというので、その東側にある雄健神社跡で下車した。回りは林で囲まれていた。その神社へは、かつて毎日のように礼拝に出向き、直立不動の姿勢で軍人勅諭などを朗読したものである。現在、その大泉門の西側に大きな振武台碑が立っていたが、無論のこと、昔はそのような石碑はなかった。
続いて、かつて一年半の間他の生徒らと起居を共にした、構内のほぼ中央に位置していた第七中隊の宿舎跡へ案内して貰った。昔の木造の建物に代わって、今はコンクリート造りの丈夫そうな建物になっていたが、何でも女性自衛官の隊舎になっているとのことで、隊則上われわれ男性は入舎できないという。それもよしと思ったところで、その隊舎の前の広場や近くの演習場で厳しく且つ激しく訓練されたことを思い出した。確か土曜の午後と日曜は休養に充てられていたが、平日は、午前中は理科系を中心にした諸学科の学習に充てられ、午後は実地の軍事訓練を課せられたと記憶している。学習では、一部の生徒が特別に英語やドイツ語を学ばされていたが、第七区隊に所属した筆者は強制的に中国語を勉強させられた一方で、他の区隊の者はロシア語を学習させられていた。その筆者も、当時は少々出来た方に認められたのか、ある時など皇族の方がわれわれ生徒の教育状況を視察に見えるというので、中国語の試験答案を清書するように指示されたこともあったのを思い出す。
それに比べて、午後の体育訓練や軍事訓練は厳しい中にも楽しかった記憶がある。ある寒い日に、雪の降る中を白い体操服一枚で色んな運動をさせられたが、風邪一つ引かなかったのもまだ若かったからであろうか。あの時は鍛えられたという思いが今に心地良く蘇るのも不思議である。また乗馬訓練も楽しいものだった。背筋を真っ直ぐに伸ばして並み足の速度で馬を駆けさせる時など、天下をとったような気分だった。ただ一度、そのような乗馬訓練中に、近くで軍事訓練をしていた他の区隊の生徒がすぐ側で小銃の空砲を打ったために、筆者の乗った馬が驚いて暴れ出したのには、一時往生したのを懐かしく思い出す。それに対して、時々真夜中に非常呼集を掛けられたり、またある時など、背嚢を背負い銃剣を帯び小銃を担ぐという完全軍装の姿で、顔には防毒マスクを着けて駆け足させられたのには、息苦しさのあまり自制が効かず、自然に小便さえズボンに垂れ流れたのを今に憶えている。しかし夕食前に、沈み行く太陽を背にして同僚らと隊伍を整え歩調を合わせながら、軍歌や校歌を声高に歌うのも心地良かった。また日曜や祭日などの休日には、外出して近郊に住む伯父夫妻の家庭を訪ねてご馳走になったり、或いは外出しない時にはキャンパス内の生徒会館へ行って、備え付けられたナポレオンの戦術書などに目を通すのも、一端の参謀将校になったような気分になって楽しかったものである。
二
そして、その女性自衛官の隊舎から東側の道路に出た時、あの決して忘れることのできない事件が蘇った。それは、すでに三月十日の大空襲で首都東京の下町は大部分が焼け野原と化し、明らかに戦局は日本に不利となってきていた昭和二十年四月七日の、確か土曜日の午前のことだった。今では殆ど忘れられてしまっていると思われるが、その旧振武台が米軍機の爆撃を受けたのである。勿論、その日は、楽しみにしていた予定も朝早くから素っ飛んだ。まもなく空襲警報が発令され、筆者も、「空襲!退避!」の合図に従って、第七中隊の隊舎の東側の道路脇に作られた数箇所の退避壕の一つへ走り込んだ。すぐに、同じ退避壕の入口近くにいて空を見上げていた同僚の一人が、「ああ、爆弾が落ちてくる」と叫んだのと殆ど同時に、ドッドッドッと地響きがして壕内の壁土が崩れ落ちてきた。辺りは土埃で真っ暗になり、やがて気が付くと膝まで土に埋まっていた。
やっとの思いで、土を掻き分けて地表に出ると、一〇メートルも隔てていない所に幾つもの大きな穴が抉り掘られたように出来ていた。その僅かな距離が生死の明暗を分けることになったのである。とっさに、昨夜、自習室で別れたばかりの同僚の向田勇次君はどうしたかと胸騒ぎがした。何人かやられたらしいとか、空爆した米軍機の主目標は振武台のすぐ北にある中島飛行機製作所の工場にあったが、余技的に振武台に爆弾を投下したようだとか、色んな情報が飛び通う。ほどなく、遺憾ながら大館区隊長をはじめ計一二名の者が戦死したという訃報を聞いた。そして、その被爆者の中に親友の向田君が入っていたとは何ということだったのか。彼も、福井県で生まれ育った筆者と同じ北陸の出身者ということで、仲よくしていたのである。彼とは、その後、生徒会館で無言のまま血色を失って眠っている姿に会わなければならなかったのには、全くやり切れない気持ちだった。その時、土色になってしまった彼の遺体に額ずきながら、彼が生前、可愛い妹がいるんだと時々語っていたのを、何ともやる瀬ない気持ちで思い出していたものである。
今年(二〇〇七)の四月中旬、向田君の郷里・富山県小矢部市に住む竹馬の友の案内で、彼が眠る市内の永伝寺の裏手にある、坂段になった墓地に赴いて二度目の墓参をした。その寺は、加賀藩主前田家とゆかりの深い古刹であるという。三十数年前に一度墓参をしたことがあったが、その時には、彼のご母堂もまだご健在で墓前へ案内していただいた。しかし今回の二度目の墓参では、それは適わず、遺憾ながらそのご母堂も昨年末に一〇三歳の長寿を全うされてすでに他界されていた。それにしても、一〇三歳というご母堂の長寿は、空爆で不慮の死を遂げざるを得なかった一七歳の向田君が、その後に生きながらえ得たであろうはずの余生を彼の母に捧げたのであろうか。そぼ降る小雨の中、筆者は、住職の読経に頭を垂れながら、向田君とご母堂のご冥福を心から祈り続けたのである。
三
旧振武台を六二年ぶりに再訪したその日、最後に案内された場所は、当初に講内に入った朝霞門に近い振武台記念館であった。その明るい外壁の記念館の前には、かつて何度も通り過ぎたことのある、キャンパス内の南側の大泉門に立っていた二本の黒ずんだ石造りの門柱が移築されていた。何でも、同記念館は、相模原の相武台にあった士官学校本科の構内に置かれていた皇族用の木造宿舎(皇族舎)を昭和五十三年三月にこの地に移築したものだという。その二階建ての館内に入ると、床が黒光りするほど磨かれていて清掃が行き届き、足を滑らそうですらあった。
二階へ上がる踊り場の上に、「振武台記念館建設の由来」と謳った説明書きが掲示してあった。何でも、予科士官学校は、太平洋戦争の始まる直前の昭和十六年十月に東京の市ヶ谷からこの地に移転してきたが、振武台とは、筆者が入学する三カ月ほど前の昭和十八年十二月に昭和天皇がこの地に行幸された折に命名されたのだそうである。二階へ上りきった所の上部に、縦一メートル・横二メートルほどの大きな額縁が飾られていて、題して「文武に励んだ振武台ゆかりの人々―2001・4・29 振武台碑委員会」とあり、五十七期の卒業生から六十一期の在校生(終戦時)までの二万名に近い先輩や同輩や後輩らの氏名が記されている。筆者の名前もあるのかなと思って探したら、その中央部分の左寄りの辺りにその氏名を見出した。何だか、面痒い気持ちだった。また奥の部屋には、当時の予科士官学校の服装を再現させた蝋人形も飾られていた。
その後、同記念館の西側に位置した“びわ湖”と称する大きな池に案内された。現在、その池は小型舟艇の操作訓練に使用されているという。池の淵には、桜の樹木が何本も植えられていて、春には桜花爛漫たる艶姿になるのだそうである。しかし六月のその日は、二、三羽の白い水鳥がたたずんでいるだけであった。池の中では沢山の亀が遊弋していたが、かつての在来種ではなく、すべて外来種の屈強な亀どもにとって替わってしまっていると聞かされた。そこから、朝霞門の出口へは近かった。
思えば、昭和二十年四月のあの空爆を受けた後、ほどなく各自の志望する兵科の決定があり、航空士官学校へ進んだ者は、戦局の一層の悪化に備えて、予科士官学校の生活を一年余りに切り上げられて卒業し、また地上兵科に決定した者たちは、一年半後に予科を卒業して本科の士官学校へ進んだ。筆者は、日露戦争に出征して二〇三高地の攻略に参加した第九師団所属の祖父が工兵であったこともあって、工兵を希望しそのように決められた。しかし、士官候補生として進学した本科・地上兵科の学習と訓練の場所は、相模原の相武台ではなくて、浅間山の火山灰に覆われた東南側の山麓に位置する陸軍演習場であった。それに、食事が玄米炊きとあって胃腸を壊してしまい、難儀したのを憶えている。そしてほどなく、同年八月十五日のポツダム宣言受諾によって終戦となり、まもなく郷里に復員した。あれからもう六二年の歳月が過ぎてしまったのだ。月日の経つのはまことに早いものである。






